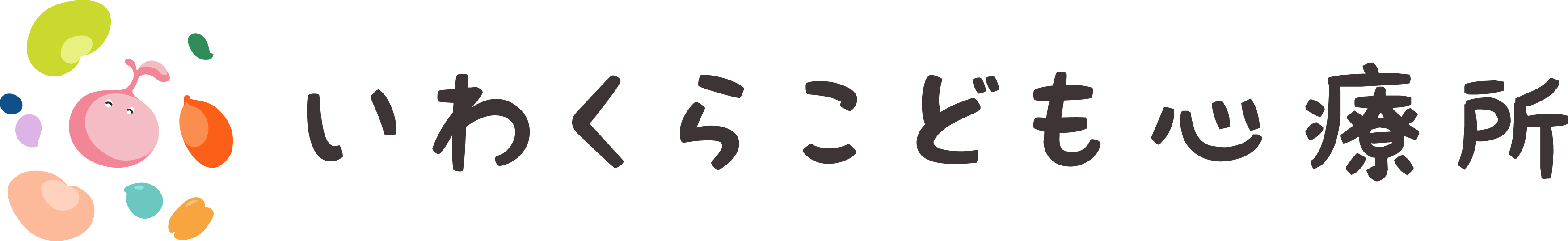発達障がい(神経発達症)について
”神経発達症”は、DSM5-TR(精神疾患の診断・統計マニュアル:アメリカ精神医学会)に記載されている診断概念です。知的発達症、自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。”発達障害”は主に自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(LD)を指します。そのため、”神経発達症”はより広い概念といえます。ここでは、神経発達症の中で主に当院で取り扱う、ASDとADHDについて説明をさせていただきたいと思います。
自閉スペクトラム症(ASD)
自閉スペクトラム症(ASD:Autism Spectrum Disorder)は、「コミュニケーションや対人関係の難しさ」と「こだわりや興味のかたより」といった特性をもつ神経発達症の一つです。ASDの診断を受けた人の中にも、非常に人見知りで緊張が強い人から、人見知りがあまりなく、積極的に人に関わっていく人まで、十人十色です。不思議に思う人もおられるかもしれませんが、その人の気質や人格全体の中で、”発達特性”は一部分に過ぎませんので、ある意味当然とも言えます。また「スペクトラム(連続体)」という言葉が示すように、その人が持っている特性の強さや種類は様々で、一昔前には「受動型」「積極奇異型」「孤立型」などにタイプ分けされることもありました。
◉対人関係の難しさ
目を合わせにくい、会話のやりとりがうまくいかない、集団行動が苦手など、人との関わりに独自のスタイルが見られます。
◉言葉の発達の偏りや使い方のスタイル
言葉の遅れ、会話が相互的なキャッチボールになりにくい、言葉の使い方や捉え方が平均的でない、などの特徴や、非言語的コミュニケーション(ジェスチャーや表情、抑揚など)の乏しさや独特のスタイルを持っていることも多いです。
◉こだわりの強さ・想像力の偏り・柔軟性の乏しさ
特定の順番やルールへのこだわり、繰り返し行動などが特徴として挙げられます。物事の見通しを立てづらく、慣れていない状況では人一倍不安になる、と言った特徴も見られることがあります。
◉感覚の偏り
音や光に敏感すぎたり、逆に鈍感だったりすることがあります。肌ざわりやにおい、味に対しても独特な好みをもつことがあります。
年齢による困りごと
以上のような特性から、乳幼児期、学童期、思春期青年期、成人期と、形を変えて様々な困りごとが起こってくることがあります。
◉幼児期
- 言葉の遅れ
- 園での集団行動や友達付き合いにうまく入っていけない
- 予定外の出来事への混乱、感覚の偏り、融通の効かなさ等から、かんしゃくが激しい
- 家庭でも、切り替えが困難であったり、会話がうまくいかず親が育てにくさを感じる
- 親との相互交流がうまくいかず、「理由がよくわからず怒られる」経験が増えがち
これにより、子ども本人も人の輪に入っていくことに抵抗を強めてしまい、他者とコミュニケーションできる機会が減ってしまうこともあります。この時期は、療育への通所や、本人の特性に合わせた声かけや支援が有効です。
◉学童期(小学校〜中学年)
- 集団生活への適応困難
形式や決まりを大事にするタイプで、臨機応変な対応が苦手
順番待ちや交代ができない - 強いこだわり・興味のかたよりによる周囲との摩擦
恐竜や電車などに非常に詳しいが、その話ばかりしてしまう
「空気を読む力」「場面の切り替え」など、暗黙の了解を読み取るスキルが求められるようになる中で、困難が生じやすい
◉思春期・青年期(中学〜高校・大学初期)
- いじめや孤立
意図せず場にそぐわない言動をしてしまい、周囲に浮く
二次障害(うつ、不安、強迫、引きこもりなど)
周囲とのズレに自覚的になる一方で、自分の特性をうまく受け止められない - 進路選択や将来像の見通し困難
「好きなこと」には熱中するが、就職や進学の具体的計画が立てづらい
定型発達の同世代集団との違いに気づき始め、不適応感を強めやすい
周囲の期待や社会的役割の増加に伴うストレスも顕在化しやすい
◉成人期以降
- 職場での対人関係の不適応
雑談や非言語的コミュニケーションが苦手、急な指示変更にパニック - 生活上の柔軟性の乏しさ
環境やルールの変更に強い不安を感じる、生活スキルにギャップがある - 心理的問題の慢性化
発達障害を「見逃されてきたこと」による二次障害(不安症、うつ病等)
この時期まで気づかれず必死でカバーしてやってきたものの、社会に出てから困難が生じ、診断が明らかになることも多いです。それぞれの時期に応じた支援や療育通所などを通じて、成人期の二次障害を予防し、特性がある中で折り合いをつけたり、工夫をしたりしてその人その人に合った方法で人生を豊かに送っていくことが重要と考えます。
診断と支援
年齢によっても支援の方法は様々です。例えば幼児期では、早期の専門的療育により、社会性や認知の発達が有意に改善することがいくつかの研究によって示されています。学童期(小学校)では、引き続いての療育への通所、養育者や教員による本人の特性の理解とそれに合わせた支援など、まだまだ周りの対応が中心です。中学校以降になれば、自分自身の特性に対する気づきや困り感も出てくるため、自己理解を通して、自身で対処できることを増やしたり、苦手なことは自ら他者を頼ったりする力をつけていくことも重要になってきます。そして何よりも、定型発達の子にとって最適な環境で作られている世の中で、やりにくさを漠然と感じながらも、どうしていいかわからず困惑してきた気持ちを分かってくれている人がいることが、その人が人生を生きていく上で大きな支えになるのではないかと考えます。
強み
ASDの特性を持った方は、同じことを実直に続けられる勤勉さ、正義感の強さ、努力家、興味のあることをとことん掘り下げて追求する職人/研究者気質、独特の感覚/感性、細部の変化に気づける、といった強みを持つことがあります。弱点として語られることもある”こだわり”も、仕事や趣味などにおいて、人生を豊かにしてくれる立派な強みでもあります。
注意欠如・多動症(ADHD)
ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder、注意欠如・多動症)は、集中することの難しさ(不注意)や、じっとしていることが難しい(多動性)、待つのが難しい(衝動性)といった特性が見られる神経発達症のひとつです。脳の働き方に由来するもので、本人の性格やしつけの問題ではありません。
主な特徴
ADHDの行動のあらわれ方には個人差がありますが、次のような特徴が見られることが多いです
◉ 不注意(集中力の維持が難しい)
- 話を聞いていないように見える
- 忘れ物やうっかりミスが多い
- 課題や遊びに集中しづらい
◉ 多動性(じっとしていられない)
- 授業中に席を立ってしまう
- 手足をいつも動かしている
- おしゃべりが止まらない
◉ 衝動性(思ったことをすぐ行動に移してしまう)
- 順番を待つのが苦手
- 相手の話を最後まで聞かずに話し出す
- 思いつきで行動し、トラブルになることも
年齢による困りごと
- 幼児期: とにかくじっとできず、走り回ったり飛び降りたり、多動・衝動性が目立つ時期
- 学童期: 授業中の集中や友人関係、忘れ物なくしもの、宿題など計画的な行動が取れないなど
- 思春期以降: 多動・衝動性は徐々に落ち着き、不注意や時間管理の難しさが続くことがある
ADHDの原因
ADHDは、脳の前頭前野や神経伝達物質(ドパミン、ノルアドレナリンなど)の働きの違いによって生じると考えられています。
診断と支援
ADHDの診断にあたっては、行動の観察、ご家族や学校からの聞き取り、心理検査などから本人の様子を把握し、生活にどの程度の困難が生じているかを多面的に評価します。
ADHDの子は、人一倍、褒められたり、楽しいことをすることで喜びが大きいのではないかと感じます。しかし、何かと怒られたり注意されたりしやすいため、自己肯定感が低下したり、注意される=注目される、の構造ができることで、いつの間にか褒められることよりも、周囲を困らせるような行動を無意識に獲得してしまいやすいところがあります。環境調整として、養育者や教員による本人の特性の理解と支援、接し方の工夫(ペアレント・トレーニング等)を行いますが、効果が不十分であれば、服薬によって行動の問題の改善を試みることもあります。ゆくゆくは、本人自身が、自身の特性を「肯定的」とまでは捉えられなくても、「まんざらでもない」と思えて、自身を嫌いにならず、特性とうまく付き合っていけることが目標と考えます。
強み
ADHDの特性を持った方は、生まれ持っての人懐っこさ、興味のあることへのエネルギーの高さ、好奇心の強さ、高い行動力などの強みを持っていることも多いです。